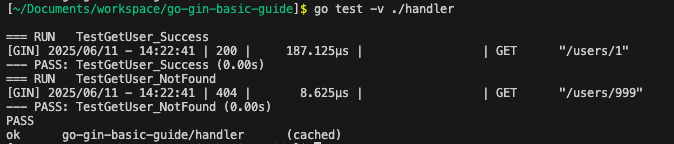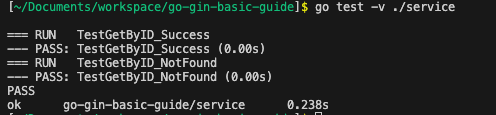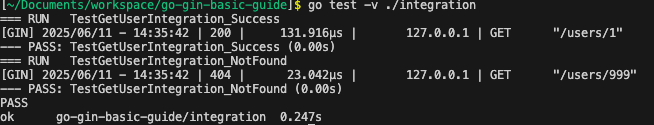この投稿はでも表示されます。
はじめに
Go × Ginの基礎を押さえたら、いよいよ次のステップに進みます。
この応用編では、実際のAPI開発で役立つテクニックや、将来的にスケーラブルなシステムを作るための設計のヒントをまとめます。
具体的には以下のようなテーマを扱います。
- 認証やバリデーションの実装例
- エラーハンドリングのパターン
- Ginアプリケーションのテスト手法
- カスタムミドルウェアの作り方
- スケーラブルなAPI設計への展望
これらを踏まえ、実務でも迷わない基礎力をさらに強化していきます。
Ginの基礎を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
Ginでよく使う便利な機能
バインディング(Binding)
Ginは、リクエストのパラメータを構造体にマッピング(バインディング)できます。
以下は、クエリパラメータを構造体にバインディングする例です。
type QueryParams struct {
Name string `form:"name"`
Age int `form:"age"`
}
r.GET("/bind", func(c *gin.Context) {
var params QueryParams
if err := c.ShouldBindQuery(¶ms); err != nil {
c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})
return
}
c.JSON(200, gin.H{"name": params.Name, "age": params.Age})
})
curl 'http://localhost:8080/bind?name=Gopher'
レスポンス
{"age":0,"name":"Gopher"}
バリデーション(Validation)
Ginは binding タグを使ってバリデーションも行えます。
type User struct {
Name string `json:"name" binding:"required"`
Age int `json:"age" binding:"gte=0,lte=120"`
}
r.POST("/validate", func(c *gin.Context) {
var user User
if err := c.ShouldBindJSON(&user); err != nil {
c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})
return
}
c.JSON(200, gin.H{"name": user.Name, "age": user.Age})
})
binding:"required"→ 必須チェックbinding:"gte=0,lte=120"→ 0以上120以下の範囲をチェック
リクエスト
curl -X POST http://localhost:8080/validate \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "Gopher", "age": 5}'
レスポンス
{"age":5,"name":"Gopher"}
リクエスト(ageを範囲外の数字に変更)
curl -X POST http://localhost:8080/validate \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "Gopher", "age": 999}'
レスポンス
{"error":"Key: 'User.Age' Error:Field validation for 'Age' failed on the 'lte' tag"}
カスタムバリデータの作成
標準のバリデーションでは足りない場合は、独自のバリデーションロジックを登録できます。
package main
import (
"github.com/gin-gonic/gin"
"github.com/go-playground/validator/v10"
"github.com/gin-gonic/gin/binding"
)
func main() {
r := gin.Default()
// カスタムバリデーション登録
if v, ok := binding.Validator.Engine().(*validator.Validate); ok {
v.RegisterValidation("customTag", customValidation)
}
r.POST("/custom", func(c *gin.Context) {
var user User
if err := c.ShouldBindJSON(&user); err != nil {
c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})
return
}
c.JSON(200, gin.H{"name": user.Name})
})
r.Run()
}
type User struct {
Name string `json:"name" binding:"required,customTag"`
}
// カスタムバリデーション関数
func customValidation(fl validator.FieldLevel) bool {
value := fl.Field().String()
return len(value) >= 3 // 3文字以上で合格
}
リクエスト
curl -X POST http://localhost:8080/custom \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name":"Gopher"}'
レスポンス
{"name":"Gopher"}
リクエスト(条件に合わない「3文字未満」の例)
curl -X POST http://localhost:8080/custom \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name":"Go"}'
レスポンス
{"error":"Key: 'User.Name' Error:Field validation for 'Name' failed on the 'customTag' tag"}
構造化されたハンドラの設計
Ginを使ったAPI開発が進むにつれて、ハンドラの構造化が重要になってきます。
ここでは、ハンドラを疎結合で保守しやすくするための考え方や、依存性注入の基本例を見ていきます。
なぜ構造化が必要
ハンドラを func(c *gin.Context) のまま書いていくと、以下のような課題が出てきます。
- データベース接続や外部サービスの依存が増える
- テストしにくい
- 可読性が下がる
ハンドラを構造体としてまとめ、ビジネスロジックをサービス層に分離することで、これらの問題を防ぎます。
サービス層とは?
サービス層は、アプリケーションのビジネスロジックを担当する部分です。
具体的な例として、ユーザー情報を扱う UserService インターフェースを用意することが多いです。
type UserService interface {
GetByID(id string) (User, error)
}
構造体ハンドラの例
ハンドラは、サービス層の依存を注入して初期化します。
type UserHandler struct {
userService UserService
}
func NewUserHandler(service UserService) *UserHandler {
return &UserHandler{userService: service}
}
func (h *UserHandler) GetUser(c *gin.Context) {
id := c.Param("id")
user, err := h.userService.GetByID(id)
if err != nil {
c.JSON(404, gin.H{"error": "User not found"})
return
}
c.JSON(200, user)
}
この例では、ハンドラは UserService に仕事を任せており、処理の中心はサービス層に移っています。
ルーティングでの利用
実際にルーティングで利用するときは、依存関係を組み合わせて渡します。
// 例: main.go
repo := NewUserRepository()
userService := NewUserService(repo)
userHandler := NewUserHandler(userService)
r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)
- UserRepository: データアクセス担当
- UserService: ビジネスロジック担当
- UserHandler: HTTPのやりとりを担当
このように分離することで、役割が明確になります。
構造化のメリット
- 依存性が明確化し、コードの見通しが良くなる
- モックの注入がしやすくなり、テストが容易に
- 役割ごとに保守・拡張しやすくなる
補足:実装例
上記イメージを実際のコードに落としたものとなります。
ディレクトリ構成(例)
go-gin-test-guide/
├── main.go
├── handler/
│ └── user_handler.go
├── service/
│ └── user_service.go
├── repository/
│ └── user_repository.go
└── model/
└── user.go
package model
type User struct {
ID string `json:"id"`
Name string `json:"name"`
}
package repository
import "my-gin-app/model"
type UserRepository interface {
FindByID(id string) (*model.User, error)
}
type userRepositoryImpl struct {
// 実際にはDB接続などを持つが、今回は省略
}
func NewUserRepository() UserRepository {
return &userRepositoryImpl{}
}
func (r *userRepositoryImpl) FindByID(id string) (*model.User, error) {
// 例として、静的なユーザー情報を返す
if id == "1" {
return &model.User{ID: "1", Name: "Gopher"}, nil
}
return nil, nil // 見つからなかった場合
}
package service
import (
"errors"
"my-gin-app/model"
"my-gin-app/repository"
)
type UserService interface {
GetByID(id string) (*model.User, error)
}
type userServiceImpl struct {
repo repository.UserRepository
}
func NewUserService(repo repository.UserRepository) UserService {
return &userServiceImpl{repo: repo}
}
func (s *userServiceImpl) GetByID(id string) (*model.User, error) {
user, err := s.repo.FindByID(id)
if err != nil {
return nil, err
}
if user == nil {
return nil, errors.New("user not found")
}
return user, nil
}
package handler
import (
"net/http"
"my-gin-app/service"
"github.com/gin-gonic/gin"
)
type UserHandler struct {
userService service.UserService
}
func NewUserHandler(service service.UserService) *UserHandler {
return &UserHandler{userService: service}
}
func (h *UserHandler) GetUser(c *gin.Context) {
id := c.Param("id")
user, err := h.userService.GetByID(id)
if err != nil {
c.JSON(http.StatusNotFound, gin.H{"error": "User not found"})
return
}
c.JSON(http.StatusOK, user)
}
package main
import (
"my-gin-app/handler"
"my-gin-app/repository"
"my-gin-app/service"
"github.com/gin-gonic/gin"
)
func main() {
r := gin.Default()
userRepo := repository.NewUserRepository()
userService := service.NewUserService(userRepo)
userHandler := handler.NewUserHandler(userService)
// ルーティング
r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)
r.Run(":8080")
}
リクエスト(ユーザーが見つかる場合)
curl http://localhost:8080/users/1
レスポンス
{"id":"1","name":"Gopher"}
リクエスト
curl http://localhost:8080/users/999
レスポンス
{"error":"User not found"}
テスト手法
Ginを使ったAPI開発では、以下の3つのレイヤーに分けてテストを設計すると堅牢です。
- ハンドラのテスト
- サービス層・リポジトリ層のテスト
- インテグレーションテスト(統合テスト)
それぞれのテスト手法とサンプルコード例を以下にまとめます。
ハンドラのテスト
Ginのハンドラをテストする際は、以下を意識します。
- 実際のHTTPリクエストを模倣できる
httptest.NewRecorder - 必要に応じて依存するサービスやリポジトリをモック化する(今回の例ではサービスをモックにする)
モックの定義
まず、service.UserService をモック化します。
これにより、ハンドラの振る舞いだけをテストできます。
package handler_test
import (
"errors"
"go-gin-basic-guide/handler"
"go-gin-basic-guide/model"
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"github.com/gin-gonic/gin"
"github.com/stretchr/testify/assert"
)
// モックサービス
type mockUserService struct {
getByIDFunc func(id string) (*model.User, error)
}
func (m *mockUserService) GetByID(id string) (*model.User, error) {
return m.getByIDFunc(id)
}
ハンドラのテストコード
実際に /users/:id エンドポイントをテストします。
func TestGetUser_Success(t *testing.T) {
// Ginをテストモードにする
gin.SetMode(gin.TestMode)
// モックサービスを準備
mockService := &mockUserService{
getByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {
return &model.User{ID: id, Name: "Test User"}, nil
},
}
// ハンドラを生成
userHandler := handler.NewUserHandler(mockService)
// Ginのルーターにハンドラを設定
r := gin.Default()
r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)
// リクエストを作成
req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/1", nil)
w := httptest.NewRecorder()
// リクエストを実行
r.ServeHTTP(w, req)
// 結果を検証
assert.Equal(t, http.StatusOK, w.Code)
assert.JSONEq(t, `{"id":"1","name":"Test User"}`, w.Body.String())
}
func TestGetUser_NotFound(t *testing.T) {
gin.SetMode(gin.TestMode)
mockService := &mockUserService{
getByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {
return nil, errors.New("user not found")
},
}
userHandler := handler.NewUserHandler(mockService)
r := gin.Default()
r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)
req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/999", nil)
w := httptest.NewRecorder()
r.ServeHTTP(w, req)
assert.Equal(t, http.StatusNotFound, w.Code)
assert.JSONEq(t, `{"error":"User not found"}`, w.Body.String())
}
テスト実行
go test -v ./handler
テストが正常に終了しました。
最後にリファクタリングとして共通のテスト用ルーター初期化関数を作っておきます。
func setupRouter(handlerFunc gin.HandlerFunc) *gin.Engine {
gin.SetMode(gin.TestMode)
r := gin.Default()
r.GET("/users/:id", handlerFunc)
return r
}
func TestGetUser_Success(t *testing.T) {
mockService := &mockUserService{
getByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {
return &model.User{ID: id, Name: "Test User"}, nil
},
}
userHandler := handler.NewUserHandler(mockService)
r := setupRouter(userHandler.GetUser)
req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/1", nil)
w := httptest.NewRecorder()
r.ServeHTTP(w, req)
assert.Equal(t, http.StatusOK, w.Code)
assert.JSONEq(t, `{"id":"1","name":"Test User"}`, w.Body.String())
}
func TestGetUser_NotFound(t *testing.T) {
mockService := &mockUserService{
getByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {
return nil, errors.New("user not found")
},
}
userHandler := handler.NewUserHandler(mockService)
r := setupRouter(userHandler.GetUser)
req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/999", nil)
w := httptest.NewRecorder()
r.ServeHTTP(w, req)
assert.Equal(t, http.StatusNotFound, w.Code)
assert.JSONEq(t, `{"error":"User not found"}`, w.Body.String())
}
テストパターンが増えた際にはこのような共通関数が必要となってきます。
サービス層のテスト
サービス層のテストでは、リポジトリをモック化してビジネスロジックのみを検証します。
例として service/user_service.go のテストコードを紹介します。
package service_test
import (
"go-gin-basic-guide/model"
"go-gin-basic-guide/service"
"testing"
"github.com/stretchr/testify/assert"
)
// リポジトリのモック
type mockUserRepo struct {
findByIDFunc func(id string) (*model.User, error)
}
func (m *mockUserRepo) FindByID(id string) (*model.User, error) {
return m.findByIDFunc(id)
}
func TestGetByID_Success(t *testing.T) {
repo := &mockUserRepo{
findByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {
return &model.User{ID: id, Name: "Mock User"}, nil
},
}
userService := service.NewUserService(repo)
user, err := userService.GetByID("1")
assert.NoError(t, err)
assert.Equal(t, "Mock User", user.Name)
}
func TestGetByID_NotFound(t *testing.T) {
repo := &mockUserRepo{
findByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {
return nil, nil
},
}
userService := service.NewUserService(repo)
user, err := userService.GetByID("999")
assert.Nil(t, user)
assert.EqualError(t, err, "user not found")
}
✅ ポイント
- サービス層では、ビジネスロジックに関わる条件分岐を中心にテスト
- データアクセスはモック化(リポジトリ層に依存しない)
テスト実行
go test -v ./service
リポジトリ層のテスト
リポジトリ層では、実際のDB(例: SQLiteやテスト用MySQL)を使うか、インメモリDBを使うことが多いです。
小さい場合はテーブルモックなどを使う例もあります。
例(簡略化した考え方):
func TestFindByID_RealDB(t *testing.T) {
db := setupTestDB() // 例: SQLiteのメモリDBを初期化
repo := repository.NewUserRepositoryWithDB(db)
// 事前にテストデータを作成
db.Exec("INSERT INTO users (id, name) VALUES (?, ?)", "1", "Test User")
user, err := repo.FindByID("1")
assert.NoError(t, err)
assert.Equal(t, "Test User", user.Name)
}
統合テスト(インテグレーションテスト)
「実際にサーバーを立ち上げて、APIのリクエスト&レスポンスを検証するテスト」です。
httptest.NewServer を使うことで、サーバーを本番に近い形で起動してテストできます。
package integration_test
import (
"go-gin-basic-guide/handler"
"go-gin-basic-guide/repository"
"go-gin-basic-guide/service"
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"github.com/gin-gonic/gin"
"github.com/stretchr/testify/assert"
)
// テストサーバーをセットアップ
func setupIntegrationRouter() *gin.Engine {
repo := repository.NewUserRepository()
userService := service.NewUserService(repo)
userHandler := handler.NewUserHandler(userService)
r := gin.Default()
r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)
return r
}
func TestGetUserIntegration_Success(t *testing.T) {
gin.SetMode(gin.TestMode)
r := setupIntegrationRouter()
ts := httptest.NewServer(r)
defer ts.Close()
resp, err := http.Get(ts.URL + "/users/1")
assert.NoError(t, err)
assert.Equal(t, http.StatusOK, resp.StatusCode)
// レスポンスボディも検証
defer resp.Body.Close()
body := make([]byte, resp.ContentLength)
resp.Body.Read(body)
assert.JSONEq(t, `{"id":"1","name":"Gopher"}`, string(body))
}
func TestGetUserIntegration_NotFound(t *testing.T) {
gin.SetMode(gin.TestMode)
r := setupIntegrationRouter()
ts := httptest.NewServer(r)
defer ts.Close()
resp, err := http.Get(ts.URL + "/users/999")
assert.NoError(t, err)
assert.Equal(t, http.StatusNotFound, resp.StatusCode)
defer resp.Body.Close()
body := make([]byte, resp.ContentLength)
resp.Body.Read(body)
assert.JSONEq(t, `{"error":"User not found"}`, string(body))
}
✅ ポイント
- Ginサーバーを立ち上げて、実際にHTTPリクエストを送る
- 依存も「実装」なので、サービス層〜リポジトリ層まで一気通貫でテスト
- E2E(外部連携含むテスト)よりは範囲が狭いが、「アプリ内部の統合確認」に最適
テスト実行
go test -v ./integration
Ginのグルーピング・ルーティング活用術
バージョニング
共通パス/認証ルールの整理
エラーハンドリングのパターン
エラーレスポンスの統一化
GinのError型の活用
認証・認可の実装例
JWT認証
ミドルウェアとしての実装
よりスケーラブルな設計へ
サービス分割、マイクロサービス化へのステップ
将来的なアーキテクチャの展望
まとめと振り返り
関連する技術ブログ
キャッシュ戦略完全ガイド:CDN・Redis・API最適化でパフォーマンスを最大化
2024/03/07Go × Echoで始めるWebサーバ構築入門:シンプル・高速なAPI開発を最短で学ぶ
2023/12/03Go × Gin 基礎編:高速APIサーバーの作り方を徹底解説
2023/11/23Go + Gin + GORMで作る記事&いいねAPI(Part 1)まずは“動かすこと優先のコントローラー”で全部入りCRUD
2025/07/13Go × Gin でMVC構成のブログ記事投稿用Web APIを構築する:基礎からスケーラブル設計まで
2023/12/03Go × Gin × MVC構成で実践する堅牢なテスト設計と実装ガイド
2023/12/04Go + Ginアプリを本番品質に仕上げる:設定・構成・CI導入まで
2023/12/06Go向け文字列スライス操作ユーティリティ「strlistutils」を公開しました
2025/06/19